会社で年末調整をしている人にとっては、確定申告はあまりなじみのないことかもしれません。
むしろ、確定申告と聞くと、「面倒くさそう」と感じる人も多いのではないでしょうか。
しかし、1年間で支払っている医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。
はじめは少し億劫かもしれませんが、納めた税金が戻ってくるならば、お得ですよね。
そこで、医療費控除の仕組みや確定申告の仕方などについて説明します。
\ 詳しいことはわからないけど、ちゃんと控除されたいなら /
そもそも医療費控除って何?
そもそも、“医療費控除“とはどういう意味なのでしょうか。
医療費控除とは、所得控除のうちの一つで、多くの医療費を支払った場合に、所得税が軽減される制度です。
つまり、医療費を多く支払った場合は、その分を所得からもマイナスできるので、結果として所得税も減額されるというわけです。
セルフメディケーション制度とは
医療費控除とよく似た制度で、セルフメディケーション制度というものもあります。
セルフメディケーション制度は2017年1月からスタートした制度で、医療費控除の特例として施行されました。
セルフメディケーションとはWHOの定義によると、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。(参考:厚生労働省)
つまり、“軽度な不調は病院などに頼らずに自分自身で治療しよう“ということです。
このセルフメディケーションを行うためには、薬をドラッグストアなどで購入する必要があります。
そして、医薬品の世帯購入額が年間12,000円を超えた場合に、所得控除を受けられる制度がセルフメディケーション制度です。
医療費控除は10万円以上で申請となりますが、セルフメディケーション制度では、12,000円以上から対象となります。
今までの医療費控除よりも対象になっている人も多いと思うので、チェックしておきましょう。
セルフメディケーション制度の対象となるOTC医薬品については、下記厚生労働省のHPに一覧表がありますので、こちらを参照してください。
ただし、こちらのセルフメディケーション制度は、医療費控除を受けた場合には申請できませんので、注意が必要です。

医療費控除の対象となる条件の目安は10万円
医療費控除額は下記の式で計算されます。
①総所得が200万円以上の人
医療費控除額=1年間の医療費合計(保険金で補填された額を除く)-10万円
②総所得が200万円未満の人
医療費控除額=1年間の医療費合計(保険金で補填された額を除く)-総所得の5%
①の式を見ると分かるように、式の中に「-10万円」が含まれています。
医療費の合計が10万円を超えないと、控除額が0円以下になってしまうので、「10万円を超えたかどうか」が医療控除を受けられるかどうかの目安になります。
支払った医療費の領収書などは1年分はすぐに捨てずに保管するとともに、合計金額をチェックしてみてください。
医療費控除には対象外になるものもある
医療費控除の対象になるものと、対象外になるものがあります。
ここからは、医療費控除の対象になるもの、ならないものを解説していきます。
医療費控除の対象範囲:家族全員分の合計額
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。
また、医療費控除の対象範囲は自分自身に使った分だけではありません。
生計を同一にする家族(扶養する家族)の分も合わせて、申請することができます。
同居している必要はないので、寮に入っている学生などのケースでも一緒に申請可能です。
自分の分だけではなく、同一生計者の分も医療費の領収書は取っておくようにしましょう。
医療費控除の対象になるもの:治療を目的とした医療費
医療費控除の対象になるのは“治療を目的とした医療費”のみとなります。
具体的な対象となる医療費を以下に列挙します。
- l 病院での診療費、治療費、入院費(健康診断の費用や予防接種の費用などは除く)
- l 入院や自宅療養をしている人の付添費用
- l 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- l 子供の歯列矯正費用
- l 医師の処方箋をもとに購入した医薬品や市販薬の購入費用(サプリメントなど健康促進や病気予防のための費用は除く)
- l 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- l 通院に必要な電車やバスなどの交通費(自家用車のガソリン代や駐車場代は除く)
- l ケガや病気の治療のためのリハビリ、はり、マッサージ費用(疲れを癒したり体調を整えたりするための施術や国家資格を持たない者による施術は除く)
- l 介護保険の対象となる介護費用
- l 助産師が分娩の介助をした場合の介助費用
- l 介護保険制度の対象となる介護サービスの自己負担額
以上のように、処方箋の薬代以外に、風邪薬などの市販薬の購入費用も控除対象となります。
また、通院に使った交通費の費用なども医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象外になるもの:病気の予防・美容目的はNG
“病気の予防のための医療費”は控除対象となりません。
こちらも以下に具体的な内容を列挙します。
- l 人間ドックなど健康診断の費用
- l インフルエンザなどの予防注射の費用
- l 歯のクリーニング、美容目的の歯科矯正、ホワイトニング
- l 美容整形の治療費用
- l 漢方薬やサプリメント、ビタミン剤の購入費用
- l マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- l 自分の都合で利用した差額ベッド代
健康診断や予防注射など、予防を目的としたものは医療費控除の対象外となります。
歯の治療についても、クリーニングや歯科矯正、ホワイトニングなどは虫歯の予防や美容などを目的としているので、対象外です。
歯科矯正については子供は医療費控除の対象となっていましたが、成人の場合は美容目的とみなされるので、医療費控除の対象外となります。
また、漢方薬やサプリメントなどは健康増進が目的で、治療目的ではないため、こちらも対象外となります。
還付金の計算方法
では、実際、医療費控除を行った場合、いくら税金が還付されるのでしょうか。
還付額を計算するには、
①医療費控除額の計算
②所得税の計算
③医療費控除による還付額の計算
という手順が必要になります。
以下、順番に説明します。
STEP1:医療費控除額の計算
先に説明しましたが、医療費控除額は下記の式で計算します。
医療費控除額=1年間の医療費合計(保険金で補填された額を除く)-10万円
※総所得が200万円以上の場合
例えば、年間の医療費合計が30万円かかっていたとすれば、医療費控除額は20万円となります。
STEP2:所得税の計算
次に所得税の計算です。
こちらは、この計算式で求められます。
課税所得額×所得税率-所得控除額
課税所得額は給与所得から基礎控除などを除いた金額になります。
整理すると、所得税を求めるには、以下の手順で計算が必要です。
給与所得の計算→課税所得の計算→所得税の計算
STEP3:給与所得の計算
給与所得は以下の式で計算されます。
給与所得=「総支給額- 非課税の手当」-給与所得控除(もしくは特定支出控除)
給与所得控除というのは、みなしの経費として所得から控除できる額のことを言います。
給与所得控除額は、収入金額ごとに下記のように決まっています。
| 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
一方、特定支出控除というのは、みなしの経費ではなく、実費で控除することができます。
控除できる対象としては、下記のものがあります。
- 自身で負担している通勤費用や接待費
- 職務に直接必要な資格の取得費用や研修費用
- 勤務に必要な衣服の購入費
例えば、サラリーマンで年収が400万円(非課税手当なし)とすると、その時の給与所得は
400万円-(400万円×30%+80,000円)=400万円-(120万円+80,000円)=272万円
となります。
STEP4:課税所得の計算
課税所得は先ほど求めた給与所得を使い、下記の式から計算します。
課税所得=給与所得+その他所得-所得控除
所得控除の代表的なものとしては、基礎控除や生命保険料、社会保険料控除などがありますが、他にも様々な種類のものがありますので、次のサイトを参照してください。→国税庁 所得控除のあらまし
基礎控除は合計所得金額(給与所得+その他所得)により、以下の様に決められています。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円~2,450万円 | 32万円 |
| 2,450万円~2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円~ | なし |
STEP5:所得税の計算
最後に所得税を計算します。
所得税の税率と控除額は、課税所得毎に下表の様に決められています。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得が224万円の場合、このような課税になります。
224万円×10%-97,500円=12万6,500円
STEP6:医療費控除による還付額の計算
最後に、医療費控除を受けた場合の還付額を計算します。
還付額は医療費控除額×所得税率で計算されます。
例えば、医療費控除額が20万円で、課税所得が224万円の場合は、所得税率が10%なので、
20万円×10%=20,000円
となり、所得税で納めた12万6,500円から20,000円が還付されることになります。
医療費控除を受けるための方法
サラリーマンなどの給与所得者が医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
確定申告には病院や薬局、ドラッグストアなどの領収書やレシートなどを提出する必要があるので、1年分の領収書などは保管しておきましょう。
また、医療費控除の申請に使用した領収書などは5年間の保管義務がありますので、申請後も破棄せずに保管しておいてください。
医療費控除の申請をするためには必要な書類(医療費控除の明細書など)は国税庁のHPのものなどを使用してください。
確定申告ソフトを使って医療費控除をより簡単に!
以上、医療費控除の意味や控除の申請の仕方について説明してきました。
医療費控除をするためには確定申告が必要ですが、提出の期限もあるため、慣れていない人はどうしても提出期日直前にバタバタしてしまいがちです。
そこで、おすすめするのが確定申告ソフトの利用です。
freee:確定申告ソフトに迷ったらfreee!

「freee」はクラウド型の確定申告ソフトです。
質問に回答していくだけで、難しい確定申告の書類を作成できる点が他の確定申告ソフトとは違う点です。
確定申告を簡単に終わらせたいけど、難しい税制度を読み解く時間がないという人におすすめです。
サポートはチャットでのサポートが標準ですが、電話でのサポートプランもあります。
【各プランと料金】
- スターター:980円/月(年額11,760円)
- スタンダード:1,980円/月(年額23,760円)
- プレミアム:3,316円/月(年額39,800円)
マネーフォワード
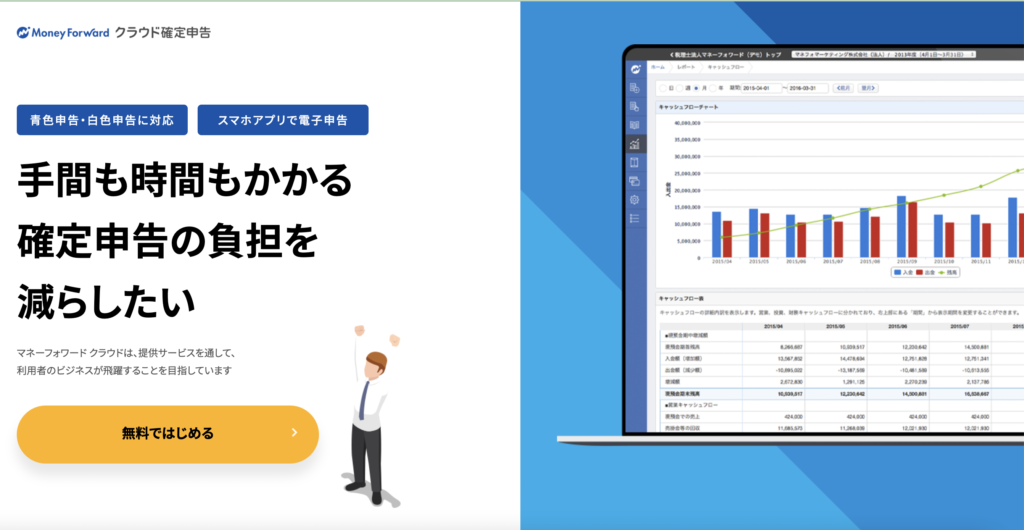
「マネーフォワード」はクラウド型の確定申告ソフトです。パソコンに何かソフトをインストールすることなく利用できます。
銀行口座、クレジットカード、通販サイトから明細を自動取得し、仕訳も行ってくれるので個人事業主の方におすすめです。
スマホからの確定申告も可能なので、簡単に確定申告を終わらせたい人はチェックしてみてください。
【各プランと料金】
- パーソナルミニ(年額プラン):800円/月(年額9,600 円)
- パーソナル(年額プラン):980円/月(年額11,760 円)
- パーソナルプラス :2,980円/月(年額35,760 円)1カ月無料トライアルあり
弥生シリーズ

「やよいの白色申告オンライン」「やよいの青色申告オンライン」は、利用している人も多く、信頼性やサポートの面でも高い評価を受けています。
登録した取引データを集計し、確定申告書類を作成することが可能です。
銀行明細やレシートのスキャンデータ、csvファイルなどを取り込むことができ、仕訳も自動で行ってくれます。
【各プランと料金】
- フリープラン:無料
- ベーシックプラン:年額4,000円 次年度以降 8,000円
操作質問可、電話・メール・チャットサポート利用可
- トータルプラン:年額70,000円 次年度以降 14,000円
操作質問・業務相談可、電話・メール・チャットサポート利用可
まとめ:医療費控除を利用して確定申告で控除を受けよう!
確定申告は毎年行うものです。
今後のためにも確定申告ソフトを導入してみてはいかがでしょうか?
